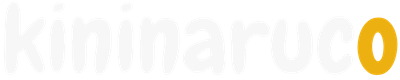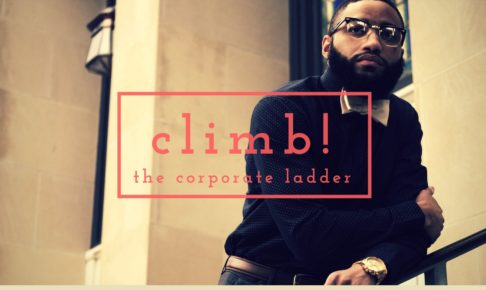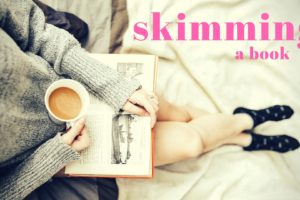プレイヤーとしての実績を上げれば、課長にはなれる。だが、部長やその先の役員を目指すには、プレイヤー時代とは違う能力が求められる。
課長は管理職の登竜門。経営幹部を目指す上で、必要な人間力を備えているかどうかを品定めされる役職だ。
仕事で成果を出し続けながら、まわりから認められ、好かれるにはどうすればいいのか? 出世する人の5つの特徴を紹介する。
mokuji
出世する人の特徴1;目上の人から信頼され、気に入られる
 企業での出世とは、目上の人に信頼され、ひいきにしてもらうことだ。そのためには、普段から上司をきちんと立て、機嫌がよくなるように振るまう「太鼓持ち」的な行動が、必要になる。
企業での出世とは、目上の人に信頼され、ひいきにしてもらうことだ。そのためには、普段から上司をきちんと立て、機嫌がよくなるように振るまう「太鼓持ち」的な行動が、必要になる。
上司が人間的にも実力的にも、自分より劣っている場合はどうすればいいのか。たとえそうであっても、上司を見下してはいけない。
そのポジションを上司に与えたのは会社だ。その上司を軽蔑するのは、会社をバカにするのと同じことだ。
上司の能力が優れているかは関係ない。上司その人ではなく、地位を敬うのだ。
組織の秩序を守る
すべての上司が有能で優れた人物とは限らない。学歴や年齢、タイミング次第で実力以上のポストについてしまうケースだってある。
だからといって上司をバカにするような態度をとっていると、会社組織の秩序を乱す人物だと見なされる。組織を束ねる重要なポストにそんな人間を起用する会社はないだろう。
会社の秩序やルールを守れない者は、役員レベルには出世できないのだ。
だが、むやみやたらと媚びへつらう必要もない。歯の浮くようなセリフでゴマをすっても、上司はその態度を見透かすだろう。
上司は、太鼓持ちをされて気持ちがいいから部下を評価するのではない。他人を立てられる人物かどうかを見ているのだ。
上司と良好なコミュニケーションを取れる人は、その様子を見ているまわりの人からも評価される。出世する人は「常に自分は見られている」ということを意識できている人間といえる。
たとえば、機嫌よく仕事をする部下と、文句を言いながら仕事をする部下がいる場合には、上司は機嫌よく仕事に打ち込める部下を引き立てたくなるだろう。
まわりの人だってそのほうが声をかけやすい。周囲と良好なコミュニケーションをとれる人物は、おのずと人望を集め、リーダー的ポジションに担ぎあげられるはずだ。
報・連・相を怠らない
 上司を立てるとは、報告、連絡、相談を欠かさないということだ。上の人間にとって、大事なことを聞かされてないのは、なによりの屈辱。上司のスケジュールを確認して、積極的にアポイントをとろう。
上司を立てるとは、報告、連絡、相談を欠かさないということだ。上の人間にとって、大事なことを聞かされてないのは、なによりの屈辱。上司のスケジュールを確認して、積極的にアポイントをとろう。
上司との面談のときには、気をつけたいポイントがある。次の3点だ。
人間は予告があると落ちつく。じっくりと聞いてもらえるはずだ。
話の長い人物だと思われると、今後の面談を後まわしにされるかもしれない。
「A案とB案があり、私は〇〇という理由でA案がいいと思うのですが」と、選択肢とセットで伝えられるとベスト。部下が真剣に考えていることが分かれば、よほどの問題がないかぎり、上司は背中を押してくれるはずだ。
早い段階で上司のお墨付きをもらえば、他部署との調整や、クライアントとの商談のさいに、「上司もそう言っています」と堂々と言える。仕事がやりやすくなるだろう。
出世する人の特徴2;判断力、決断力が優れている
 部長や役員クラスになると、迅速で的確な判断力、決断力が要求される。といっても、常に会社の命運を左右するような重要な判断をしているわけではない。ほとんどは、小さな決断を次々と下していくだけだ。
部長や役員クラスになると、迅速で的確な判断力、決断力が要求される。といっても、常に会社の命運を左右するような重要な判断をしているわけではない。ほとんどは、小さな決断を次々と下していくだけだ。
決断することに過度なプレッシャーを感じる必要はない。役員だって成功と失敗をくり返してきたはずだ。場数を踏めば、慣れてくる。構えすぎない姿勢が大事だ。
出世できるのは、即断即決できる人間だ。決断を迫られる場面になって、ようやくどうするかを考え始めるのでは遅い。間違えたら修正すればいいのだ。
スピード感をもって意思決定をするには、とにかく場数を踏むこと。失敗を含めて、たくさんの経験を積むことだ。
決断力のある人は、腹をくくって即実行に移す。場数を踏めばその分失敗は多くなるが、それでいい。
トーマス・エジソンは電球を発明するまでに、1万回もの失敗をかさねたと言われている。しかし彼はそれを失敗とは考えず、「うまくいかない方法を1万通り見つけただけ」と言ってのけた。
自動車王ヘンリー・フォードも何度も挫折を経験したが、「失敗は挑戦するためのよい機会」と意に介さなかった。
偉人たちも場数を踏んで、試行錯誤をくり返している。僕らも恐れる必要はない。
出世する人の特徴3;臨機応変に対応できる
 出世する人は、あらゆるケースを予測して、その精度を高める努力をしている。まわりの人には不測の事態だとしても、彼らにとっては予想の範疇であり、そもそも不測の事態だとは思ってもいない。
出世する人は、あらゆるケースを予測して、その精度を高める努力をしている。まわりの人には不測の事態だとしても、彼らにとっては予想の範疇であり、そもそも不測の事態だとは思ってもいない。
ビジネスでは、あらゆるケースを予測して、その精度を高めるように努める必要がある。それが不測の事態を減らす1番の方法だ。
機転のきいた対応ができる人は、さまざまな予測を立てる中で、メインの計画以外にも、いくつかの代替案を用意している。計画や決断に対し、状況の変化に応じて柔軟に修正できるのだ。
もし、まったく思いもよらないことが起こったときには、開き直ることも必要になる。開き直るといっても、破れかぶれになるという意味ではない。
ビジネスでは、ときに自分の力ではどうしようもない状況が起こる。成功、失敗に限らず、自身の努力や意思を超えた不思議な力が作用することがある。
挽回する努力は全力ですべきだが、ときには開き直りも大切なのだ。不測の事態を恐れ臆病になり、チャレンジすることを忘れないようにしたい。
出世する人の特徴4;忍耐力がある
 人間の資質は、逆境に置かれたときにこそ試される。
人間の資質は、逆境に置かれたときにこそ試される。
企業人として生きていれば、関連会社に出向させられたり、納得できない命令、評価を下されたりと、理不尽な経験をすることがある。大切なのは、楽観的であること。辛い状況でも腐らず、投げ出さず、置かれた環境でベストを尽くすことだ。
たとえ困難な状況でも、必ずチャンスはやってくると考える。逆境を単なる不運ととらえるのではなく、そこに何かしらの意味を見出せるかどうかで、その後の人生は大きく変わる。
経営者の中には、トイレ掃除やゴミ拾いなどを自ら行う人がいる。彼らは、本来の自分の地位より下の立場に身を置くことで、謙虚な姿勢を忘れないように心がけているのだ。
理不尽な経験も、大きくジャンプするために少し屈んでいるのだと考えれば、苦にはならない。沈んだあとは浮き上がる。人生とは、そういう風にできているのだ。
出世する人の特徴5;同僚や部下に味方が多い
役員に求められる資質として、多くの偉人たちが共通して述べているのは、他者を思いやる姿勢だ。思いやりの心が、同僚や部下からの信頼を勝ちとる。
リーダーになるのは、他人を思いやれる人

スティーブン・R・コヴィー博士の『7つの習慣』には、第4の習慣として「相手の利益を考えよ」と書かれている。
「人に信頼され、味方になってもらうには、相手のためになることをやりなさい、それが組織を動かす習慣だ」とコヴィー博士は言っている。自分の利益ばかり考えているようでは、役員にはなれない。
中国の古典『論語』は「仁・義・礼・智・信」の5つの徳のうち「仁(思いやりの心)」がもっとも大切だとしている。
ピーター・ドラッカーも著書『現代の経営』の中で「経営とは真摯さである。真摯さに欠けた者をリーダーにしてはならない」と述べている。真摯さとは、まじめでひたむきなこと。思いやりに通ずる姿勢だ。
多くの偉人たちが、自分のことよりまず相手のことを考えよと言っている。この資質は、生まれ持ったものではない。習慣で身に付けるものだ。利他(自分を犠牲にしても他人の利益を図ること)を心がけて行動すれば、やがて他者を思いやる態度が身につく。
部下を信頼し、主体性を引きだす
 上から目線で、頭ごなしに叱りつければ、部下からの信頼は得られない。命令したい気持ちをグッとこらえて信頼することで、部下の主体性をうながす。
上から目線で、頭ごなしに叱りつければ、部下からの信頼は得られない。命令したい気持ちをグッとこらえて信頼することで、部下の主体性をうながす。
フィードバックには5つの段階がある。たとえば、遅刻常習犯の部下に対しては次のようになる。
部下の主体性を尊重するには、できるだけ第1段階の指摘にとどめるのがいい。多少時間はかかっても、事実だけを伝え続け、部下がみずから改めるのを辛抱強く待つのだ。
人に信頼されるには、まずは自分が相手を信頼すること。僕はあなたの味方だ、困ったことがあれば相談してほしいという姿勢を見せることだ。
人間は、何かをしてもらった相手には恩を返したくなる。心理学では「返報性の法則」という。この心理は、上司と部下のあいだにも成り立つ。部下との関係が良好になれば、チームの成績も上がる。
部下は、上司には話しかけづらいもの。上司からの働きかけが壁を取り払うきっかけになる。
出世する人に共通する5つの特徴;まとめ