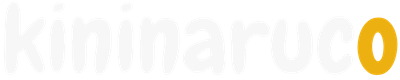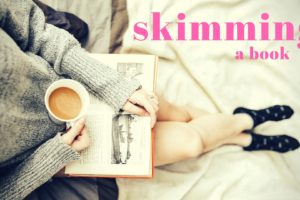仕事、勉強、家事、などなど。がんばらなくちゃいけないのはわかっているけれど、ときにはやる気がでない日だってある。人間だもの。1日や2日くらいはどうってことない。休もう休もう!
だけど、やる気がでない日って毎日だったりする。月曜日にスタートダッシュに失敗し、低調なまま火曜日、水曜日を過ごす。木曜日に再びエンジンをかけようとするものの、すぐにエンスト。金曜日には来週からがんばればいいと開き直る。よくあるけれど、こんなのはよくない。
どうしてやる気がでないんだろう、と悩む日々。自分がきらいになりそうだ。やる気スイッチはどこにある?
そんな人にぴったりのやる気診断テストがある。やる気がでない原因をズバリ特定する、そんな診断テストがここにはあるのだ。
mokuji
そもそもやる気ってなに? やる気がでる仕組み
やる気診断テストをはじめる前に、やる気がでる仕組みについてざっくりと説明する。教科書的な内容になる。興味がある人は続きを読み、興味がない人は続きを読まず、やる気診断テストに進んでほしい。
やる気スイッチは脳にある
やる気がでたり、でなかったり。やる気スイッチのオンオフは脳がやっている。むずかしくいうと、脳内の化学変化が原因だ。脳内にはやる気ホルモンと呼ばれる神経伝達物質がある。正式名称は甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン(TRH)という。
TRHはやる気のレベルによって分泌される量が変わる。やる気があるときにはドバッと出て、やる気がないときにはチョロっとしか出ない。出たり出なかったりする。
やる気ホルモンは、楽しさ、好奇心、お金といった要素で分泌される。ほかには、過去に仕事でうまくいった経験(成功体験)もやる気を生む要素になる。対して苦手意識はやる気の邪魔をする。
ドーパミンとノルアドレナリン
次はやる気に関する脳の神経回路を見てみよう。僕らの体には多くの神経が通っている。そのなかには無随意神経がある。無随意神経は脳幹を出発点としてABCの3つの経路に分かれる。
やる気と集中力に関係するのはA系列の神経回路だ。とくにA6神経とA10神経ではカテコールアミンが大量に分泌される。カテコールアミンはホルモンの基本骨格。わかりやすくいうと、進化前の状態だ。進化後には、脳を覚醒させて快感をあたえるドーパミンやノルアドレナリンに変わる。
やる気がでると、A10神経はドーパミンを大量に分泌する。ドーパミンは快感と創造性を原動力で、脳を覚醒させる働きを持つ神経伝達物質だ。
A10神経はほかの動物にもあるが、あまり発達していない。ドーパミンは人間以外の動物ではほとんど分泌されず、脳の前頭連合野でのみ消費されることがわかっている。ドーパミンこそが人間が感じる好奇心、楽しさ、創造意欲を引き起こし、やる気と集中力を支えている。
A6神経はおもにノルアドレナリンを分泌する。ノルアドレナリンは脳内だけではなく、腎臓の上あたりにある副腎でも生成される。全身に広がる神経(交感神経)で分泌されるホルモンだ。
仕事をしよう、勉強をしよう。やる気がでているときには、ノルアドレナリンは全身を駆け巡る。ドーパミンと同様に、やる気を支える大切な物質なのだ。
休息なし、やる気なし
ドーパミンやノルアドレナリンを分泌させるには、脳を健康な状態にしておくのが大事だ。脳の健康には休息が欠かせない。ストレスを溜めない状態を保つことで、やる気を高め、集中力を回復することができる。仕事や勉強をするときにはときどき休憩しよう、といわれるのはこのためだ。
適度な睡眠はやる気をだす鍵となる。A系列の神経伝達物質は、睡眠をとると脳内で生成・蓄積される。血中濃度は起床後がもっとも高い。やる気は眠っているときに作られるのだ。
適度な運動もドーパミンやノルアドレナリンを分泌する鍵となる。おすすめは散歩。ジョギングもいい。時間は10分20分でかまわない。
大きな筋肉を動かすほど、脳は刺激される。大きな筋肉が集まるのは下半身だ。散歩は気分転換になるし、なにより脳によい。とくに朝の散歩は、澄んだ空気や朝日を浴びることで脳を活性化させ、脳内の神経物質も存分に刺激してくれる。
やる気診断テスト
やる気診断テストは全部で30問。各質問には1〜5の点数をつける。点数が多いほどYES、少ないほどNOだ。
やる気診断テストの結果は、仕事のやる気が出ない原因を特定するのに使う。そのときに足し算をする。計算がしやすいように紙とペンを用意して、縦×横が5×6マスの表を作る。下の図のような感じだ。

では、やる気診断テストをはじめよう。
- 人に自慢できる特技がある
- 将来の夢に向かって突き進むエネルギーに満ちている
- 日頃からやる気をだすための工夫や勉強をしている
- お金にはそれほどこだわらない
- 人を叱るより褒めることを優先させている
- 週末は疲れた体を休め、翌週の英気を養うようにしている
- なんでもそれなりにこなせる器用貧乏なところが自分の欠点だ
- 自分の夢をいつも心に秘めて行動している
- ピンチになってもやる気が失せることはない
- いつかは会社のトップに立ってやるという上昇志向が強い
- 家族や仲間とのコミュニケーションを大切にしている
- 仕事の効率化や時間を守る意識がうすい
- 得意分野を極めることに全力を尽くせる
- 普段は一生懸命がんばるが、ときには目標を見失うことがある
- 最近まったくやる気がでない
- ほかの人より物欲が旺盛である
- 相手の立場に立って考えることができる
- 体調管理には気をつけている
- 忙しくて自分のやりたいことに没頭できない
- 自分はなにごとにも凝り性だと思う
- 使命感が強く、途中で投げ出すことはない
- より良い生活を家族にさせたいと思う気持ちは人一倍強い
- 対人関係のトラブルを起こしやすい
- 机の上はいつも整頓されている
- 目標を設定して行動するのが苦手だ
- 夢があるから少しくらいの逆境ではへこたれない
- 朝起きたときに「今日もがんばろう!」という気持ちになる
- 報酬や肩書きは自分にとって大きなモチベーションになる
- いま、職場の人間関係で深く悩んでいる
- 仕事をしやすい環境にはつねに気を配っている
すべての点数を合計すると、現在のモチベーションタイプがわかる。
- 120点以上 – 「完全燃焼タイプ」
モチベーションが高く、成果も上がっている。いまは毎日が充実しているはず。 - 119〜100点 – 「燃え尽きタイプ」
モチベーションは平均レベル以上だけど、なにかと悩みが多い。目標が高すぎたり、完璧主義だったりして、できていない部分にばかり目がいく。少し肩の力を抜くといいかも。 - 99〜80点 – 「割り切りタイプ」
モチベーションはそれほど高くない。仕事がうまくいかないのは、能力・スキルではなく気持ちの部分が原因である可能性が高い。 - 80点以下 – 「挫折タイプ」
モチベーションが低く、成果も上がっていない。なんとかしたほうがいい。
やる気がでない原因を特定する
やる気診断テストがおわったところで、やる気がでない原因を特定していこう。
やる気は6つの要素で成り立っている。
- 才能・特技
- ビジョン・目標
- 内的モチベーション
- 外的モチベーション
- 人間関係
- 環境設定
たとえばこんなイメージだ。
やる気を製造する機械がある。機械からは6本のコードが伸びている。すべてのコードをコンセントにつなぐ必要はない。1本つなぐだけで機械は動く。だけど、たくさんつなぐほうがやる気の製造量は増える。1本のときは10%、3本のときは40%、6本のときは100%という感じに、相乗効果もある。
やる気診断テストは、この6つの要素をもとに作っている。やる気診断テストの点数を縦に足すと、どの要素がやる気の足をひっぱっているかがわかる。

下の表のように6つの要素をグラフ化すると、やる気がでない原因が見えやすい。また、現在の自分のやる気を支えている要素もわかる。

やる気の6つの要素について詳しく見ていく。
a 才能・特技
この項目には、興味や関心、好奇心、過去の成功体験なども含まれる。
才能や特技が生かされていると感じると、人はやる気がでる。興味がない仕事をやらされているときはやる気がでない。これは説明の必要もない。誰もが身をもって知っている。
好き嫌いはやる気にとっては特別な感情だ。やる気がでるのは、その対象が好きだからという場合が多い。仕事でも勉強でもスポーツでも、そうだ。なにかに対してやる気をだそうと思うなら、そのなにかを好きになることが肝心だ。
嫌いと感じるときは、食わず嫌いの場合も多い。理由をうまくは説明できないけれどなんとなく嫌い、なのだ。嫌いかも、という先入観がやる気の邪魔をしている。
そういうときは、対象に興味を持つのがひとつの解決策になる。なんとなく苦手だった人とゆっくり話をしてみたら意外といい人だった、というのはよくある話だ。これは相手が人ではなく、仕事でも勉強でも起こり得る。
先入観を捨て、興味を持ち、ちょっとでも好きなところを見つけることができれば、そのちょっとの部分がやる気がでるきっかけになるのだ。
過去の成功体験もやる気には欠かせない。人がやる気をだすのは快感を得るためだ。やる気をだして努力をしたさきには、売上が10%伸びた、テストで100点とれた、3kg痩せた、ゲームをクリアした、といった達成感が待っている。
快感は癖になる。成功体験がある人は、達成感をもういちど味わいたいと思う。つぎもがんばろう、とやる気がでる。だからまた成功する。やる気と快感はぐるぐると循環するのだ。
成功までの道のりがきびしいほど、達成の喜びは大きい。快感が大きいほど、やる気は強くなる。大きな成功をした人ほど、さらなる成功が手に入るのだ。
b ビジョン・目標
ビジョン・目標は、将来の夢や仕事の目標を指す。
目的があるから、人はやる気がでる。やりたいことがはっきり見えないと、やる気のエンジンはかからない。お金持ちになりたい、かしこくなりたい、といったぼんやりしたあこがれだけではやる気はでないのだ。
目的とは具体性だ。旅行に例えると、目的とは行き先であり、交通手段だ。目的地を決めるだけではなく、何時に起きて、何時に家を出発するのか。何を持っていくのか。どのルートを選び、どの電車に乗るのか。目的とは、これらを具体的に決めることだ。
目的はやる気の向かうゴールだ。ゴールがないと動きたくても動けない。どこかに行きたいではどこにもたどり着けない。車に乗り込みエンジンをかけても、目的地が決まらないかぎりは、アクセルは踏み込めないのだ。
c 内的モチベーション
内的モチベーションは自分の心の底から現れるやる気だ。根底には成長したいという純粋な気持ちがある。そういう意味では理想的なやる気だ。
子どもたちはゲームに熱中する。それはゲームが好きで、楽しくて、わくわくするからだ。ゲームをしても、お金をもらえるわけでもなく、親にほめられるわけでもない。むしろ叱られる。
それでもゲームをやる。ゲームオーバーになってもそこでおわりではなく、ミスの原因を分析する。次こそはクリアしてやるぞ、とやる気だ。何度もチャレンジする。これが内的モチベーションだ。
次に説明する外的モチベーションが内的モチベーションに変わるときもある。
ダイエットのためにジョギングをはじめたのに、目標体重に達したあとも走るのをやめない人がいる。体型維持のためにというのもあるだろうが、たいたいはジョギングの楽しさに気づき、もっと早く走りたいと思うからだ。いつのまにかダイエットではなく、走るのが目的になっているのだ。
d 外的モチベーション
外的モチベーションは外から与えられるやる気だ。報酬、肩書き、評価、名誉などがある。自分ではコントロールできない、あるいはコントロールしにくいものが多い。仕事で結果をだしても、給料が上がるとはかぎらない。
外的モチベーションは悪者にされることが多いように感じるが、それは違う。
欲はやる気のエンジンになる。欲張りなほど、やる気にはよい。満たされているときには人はやる気がでないからだ。無関心、無気力、無感動になる。お腹がいっぱいのときには食欲を感じないように、いまの自分に満足すると、いま以上を目指さなくなる。無欲ではやる気はでなくなり、成長も止まる。
欲は人が生きる力だ。むかしの人はハングリー精神が強かった。戦後のなにもない時代を経験した人たちだ。食べるものもない、着るものもない。生きるために彼らはやる気をだした。やる気がない人は生きていけなかった。
彼らの子供たちは豊かさを求めた。テレビ、冷蔵庫、車といった豊かさの象徴を手に入れるため、やる気をだした。勉強をがんばり、仕事をがんばった。日本は豊かになった。豊かになりたいという彼らの欲が、いまの日本を作ったのだ。
僕らは満たされた時代に生きている。コンビニがある。スマートフォンがある。食うにも遊ぶにも不自由はしない。ひとりでも生きやすくなった。結婚をする理由もない。女性にもてるためのおしゃれもいらない。かっこいい車もいらない。これ以上はなにもいらない。僕らには欲がないのだ。
やる気をだすには、いまに満足してはダメだ。もっと欲張りになろう。ビルゲイツくらいお金がほしい、おしゃれな服がほしい、かっこいい車がほしい、モデルみたいな彼女がほしい、高級マンションがほしい。あれもほしい、これもほしい。欲は人をやる気にさせる。
e 人間関係
仕事では人との関わり合いは避けられない。仕事でめんどうくさいと思う出来事の多くは、人間関係が原因で起こる。営業だったらこんな感じだ。
- 生産が追いつかないから納期を遅らせてくれ、と工場から電話がかかってくる。
- 納期を遅らせてほしい、と担当企業に頭を下げる。
- 落とし所を交渉するために、工場と担当企業を行ったり来たり電話する。
- なんとかなったときは、イレギュラーに対応してくれてありがとう、と感謝する。
- なんともならないときは、上司に相談する。
- それでもダメだったら、上司を連れてあやまりに行く。
- 怒られる。
- 今後納期が遅れないように、対策を求められる。
- 次の会議で報告をして、言い訳をする。
- ほかの仕事が遅れる。
人間関係の悩みはやる気を消耗する。車の運転に似ている。すべての信号機が青色のときはスムーズに進むけれど、どこかが黄色だったり赤色だったりしたときは思うようには進めない。大きなストレスになる。
ストレスはやる気の敵だ。信号で止まるたびにやる気は下がりつづけ、いつかは底をつく。やる気のためには、人間関係はいつも青色に保ちたいものだ。
f 環境設定
環境設定は仕事の集中力に関わる。目の前の作業に集中できるかは、職場の環境やその日の体調などに影響を受ける。
ただ、集中できる環境には個人差がある。たとえば、一般的には静かなオフィスや整頓されたデスクが集中できる環境だといわれている。
だけどなかには、音楽が流れているカフェのほうが仕事がはかどる人もいる。デスクの上は多少ごちゃごちゃしているほうが落ち着く人がいる。あるいはお気に入りのペンさえあれば集中できる人もいる。
万人にあう環境はないのだ。靴選びのように、自分にぴったりの環境を探す。ぴったりの靴が見つかれば、歩き続けても足は疲れない。目の前の作業に集中できる。
まとめ やる気がでない原因は特定された!
やる気がでない原因は特定された。自分に足りないやる気要素を補ってあげると、人生は無敵になる。
エンストの心配はない。僕らには6つのやる気エンジンがある。月曜日にスタートダッシュに成功し、絶好調のままに火曜日、水曜日、木曜日、金曜日を突き抜ける。スピード違反には気をつけよう!
参考書籍:
- 『「やる気はあるのに動けない」そんな自分を操るコツ』児玉光雄
- 『やる気を生む脳科学』大木幸介