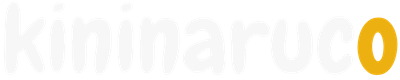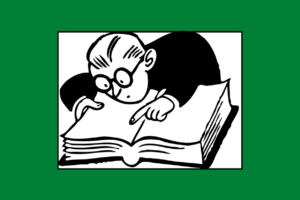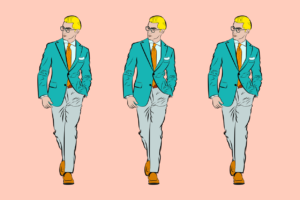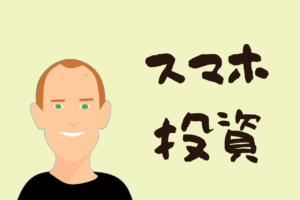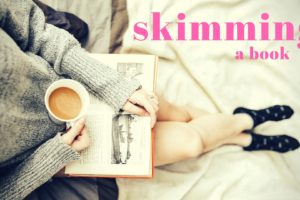「知ったかぶり」は嫌われる。だけど、社会人にとっては「知らない」「わからない」は禁ワードだ。とくに会社の上司や、取引先の重役の前では、口が裂けても言えない。少ない知識でその場をごまかし、乗り切るしかないのだ。
読んでない本や、よく知らないニュースを、無知を見抜かれずに堂々と語るにはどうすればいいのか? 一流の知ったかぶりの技術、伝授します。
mokuji
知ったかぶりは危険?
 よく知らない話題で盛り上がっているとき、なんとなく仲間はずれになるのは嫌だからと、適当なところであいづちを打ってみる。知ったかぶりは、日本で生きていく上で大切なスキルだ。
よく知らない話題で盛り上がっているとき、なんとなく仲間はずれになるのは嫌だからと、適当なところであいづちを打ってみる。知ったかぶりは、日本で生きていく上で大切なスキルだ。
だが、知ったかぶりには危険が付きものだ。あいづちを打っていると突然、グループのひとりから声をかけられる。「〇〇君はどう思うの?」。和やかな雰囲気が一転、修羅場へと変わる。
友人との会話だったら「実は知らないんだ」と答えればいい。「なんだよ、知ったかぶりかよ」と笑い話で済む。だけど、相手が会社の上司や、取引先のえらい人だった場合、いまさら「知りません」なんて口が裂けても言えない。というか、言っちゃいけない。社会人にとって「知らない」「わからない」は禁句だ。
このような修羅場をさけるためにも、正しい知ったかぶりの方法を身につけておこう。
正しい知ったかぶりの方法
 知らないという事実を悟られたくないとき、もっともやってはいけないのは、黙ってしまうこと。ボロが出るのを恐れてずっと黙っていると、「実はコイツ、何にも知らないんじゃないのか?」と疑われる。とにかく何かしゃべったほうがいい。
知らないという事実を悟られたくないとき、もっともやってはいけないのは、黙ってしまうこと。ボロが出るのを恐れてずっと黙っていると、「実はコイツ、何にも知らないんじゃないのか?」と疑われる。とにかく何かしゃべったほうがいい。
とはいっても、知識もないのに何を話せばいいのか? 効果的なのは、質問をすることだ。
たとえば、話題が仮想通貨の場合には「最近の仮想通貨ってどうなんですか? 何か注目されている仮想通貨はありますか?」と、こちらから積極的に質問を投げかけていく。先手を打つわけだ。相手にいろいろ話をさせて、自分の知っているキーワードが出てくるのを待つ。知っている言葉が出てきたときには、自分から話しはじめればいい。
「それ気になっていたんです。もっと教えてくれませんか?」と聞いてみるのもいい。知らないことはバレてしまうが、興味を示すことで、話題に対して無関心と思われずに済む。
「わかりません」「知りません」とは絶対に言ってはいけない。あなたの話には興味もないし、知りたくもないと言っているのと同じだ。そんなつもりで言っていなくても、相手にはそのように伝わってしまう。
まったく知識がない状態では、相手に話をあわせて、知ったかぶりで会話を続けるのはむずかしい。聞きなれないワードでも、それが(たとえば芸能、スポーツ、経済など)どのカテゴリーに属する話題なのかくらいは知っておきたい。
一流の知ったかぶりになる技術

誰も覚えていないことを詳細に語る
事実だと信じ込ませるには、誰も覚えていないようなことを詳細に語るのが有効だ。
たとえば、はじめて会ったときのことを覚えていると相手に信じてもらいたい場合には「その日、僕はネイビーのネクタイをしていて、カバンの中にはポカリスウェットが入っていたんです」と自信満々に語る。聞いている側は、それがウソかホントか確かめようがない。「そんな詳細まで覚えているなら、本当だろう」と信じてしまう。
この方法は、上司に「これを読んでおきなさい」と読書を勧められたときにも有効だ。分厚い本を全部読まなくても、本題には大きく関係しない箇所を探して、その部分を徹底的に覚える。感想を聞かれたときには、その部分を詳細に語る。力強く語れば語るほど、まるで読破したかのような雰囲気を演出できる。
得意分野に持ち込む
社会人には「知ってはいるけれど、よく理解していないこと」について語らなければいけないときがある。たとえば、最近の流行に対して「〇〇君は若いから△△のこと詳しいんじゃない?」といった上司からのキラーパスだ。「知らない」といえば、場の空気も、上司の機嫌も悪くなってしまう。こんなときは、話を少し横にずらして、自分の得意分野の話題に持ち込むといい。
「△△を野球でたとえると、〇〇チームの〇〇選手が〇〇するような感じです」と言ってみる。本題に対する知識が多少あいまいでも、たとえる対象に関する知識が豊富な場合には、説得力があるように聞こえる。
このとき、ふざけた雰囲気を出してはいけない。ごまかしているのが伝わってしまう。まじめに語るからこそ、知ったかぶりには説得力が生まれるのだ。
テンションは一定に保つ
ウソをついて誤魔化そうとするとき、人間の行動は2種類に分かれる。ひとつは、注目を浴びないように控えめに行動する人。もうひとつは、あえて目立とうとする人だ。
だが、人をだます場合には、過剰な行動は取らないほうがいい。突然黙り込んだり、急にソワソワしたりする人がいれば、何かを隠していると疑うだろう。自信があるときには堂々と語り、自信がないときには口数が少なくなるのでは、怪しすぎる。知ったかぶりたいときには、テンションを一定に保つことが重要だ。
一流の知ったかぶりになる情報収集術

一流の知ったかぶりになるには、広くて浅い知識が必要だ。できるかぎり手間をかけずに、広く浅い知識を集める方法を紹介する。
個人ブログを読み比べる
読んでいない書籍や、観ていない映画について語りたいときに便利なのは、インターネットだ。まずは公式のホームページであらすじなどをささっと確認する。次は、書籍などのタイトルに「あらすじ」や「要約」などのワードを追加して、Googleで検索し、良さそうな個人ブログを5つほど読み比べる。
いくつかのブログで内容が重なっている部分が、だれもが印象に残る重要なポイントだ。2つ以上のサイトで重複している意見をつなぎ合わせれば、短時間でツボを押さえた感想ができあがる。
小学生向けの新聞を読む
時事ネタをすばやく把握するには、小・中学生向けの新聞がおすすめ。むずかしいキーワードには必ず注釈がついているので、自分で調べる手間がはぶける。よく知らない分野の記事でも楽々と理解できる。
古典はまんがで学ぶ
古典と呼ばれる名著の内容を知っておきたいときには、まんがを読めばいい。
とくに『まんがで読破』シリーズ(イースト・プレス)は完成度が高い。文学、哲学、経済学、科学、歴史書、自伝など、幅広いジャンルで130冊以上発売されている。文庫本サイズで値段もお手頃だ。
週刊誌の中吊り広告をチェックする
通勤に電車を利用している人は、週刊誌の中吊り広告をチェックする。コンビニの雑誌コーナーで表紙のななめ読みをするのも有効だ。
週刊誌には、旬のキーワードが厳選して取り上げられているので、時事ネタをまとめて仕入れることができる。
SNSを利用する
Twitterなどのソーシャルメディアでニュースサイトのアカウントをフォローする。このとき、ニュースに対してたくさん意見を書き込んでいる個人のアカウントも合わせてフォローしよう。興味のない分野では、彼らの意見をそっくりそのまま頂いてしまえばいい。
一流の知ったかぶりになる記憶術

感情にひもづけて覚える
うれしかった、悔しかったという感情をともなった記憶は定着しやすい。ニュースなどはそのまま覚えようとするより、そのニュースに対してコメントしているSNSのアカウントをチェックする。「この人の言う通りだ」とか「おかしな意見だ」とかいう感情がフックとなって、あとでニュースを思い出しやすくなる。
情報を発信する
新しい言葉を覚えたら、友人との会話で積極的に使ってみる。「この言葉知っている?」と家族に聞いてみる。家族も友人もいなければ、独り言をつぶやいてみる。
話すために、頭の中で話を組み立てているうちに、情報が整理されていく。口に出すことで、頭の中で繰り返しているよりも記憶が深まる。
あきらめてメモをとる
感情にひもづけても、だれかに話しても覚えられない場合には、手を動かすしかない。覚えられない単語をジャンル別にノートに書き込んでいこう。
白いページが少なくなり、書きおわったノートの冊数が増えてきたとき、知ったかぶりは卒業して、真の情報通になっているはずだ。
浅い知識を見抜かれない、一流の知ったかぶりになる方法;まとめ
自分の中に情報を溜め込むだけでは、一流の知ったかぶりとは言えない。「知っている」とまわりにアピールするために、情報を得たときは即座に発信しよう。そのほうが記憶にも定着しやすい。
友達にすぐ話したり、ソーシャルメディアに書き込んだりする。覚えた言葉をTwitterでつぶやくだけでもいい。ファロワーから反応があれば、より知識が増えるだろう。