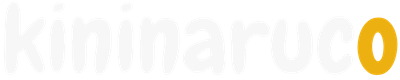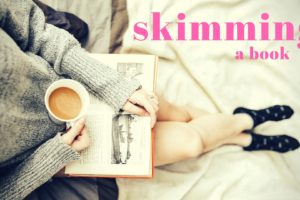情報が次から次へと押し寄せてくる時代。新聞やテレビはまだしも、インターネット上にはウソかホントかわからない情報が溢れている。
こんなときだからこそ、僕らには信頼のできる情報を効率よく集める能力が求められている。
どうすれば良質な情報を見抜くことができるのか。短期間で効果が出る、情報力の高め方をお伝えする。
mokuji
情報収集の基本は、新聞の流し読み
 情報力を高め、その情報の要点を見抜く力を身に付けたい。まずは新聞を読もう。
情報力を高め、その情報の要点を見抜く力を身に付けたい。まずは新聞を読もう。
経済紙でも一般紙でも構わないが、一紙を選ぶとすれば「日経新聞」がおすすめ。日経新聞は、多くの会社が購読しているので、わざわざ買わなくて済む。
侮れないのが小学生、中学生向けの新聞。むずかしいキーワードには必ず注釈がついているので、手始めにはいいかもしれない。
情報力を高める新聞の読み方
はじめに一面記事に目を通そう。一面記事は、各社がその日1番重要だと判断した記事だ。世間の関心も高い。まずは重要度の高いトピックスから抑えていこう。
つぎはリード文付きの大きな記事を読んでいく。紙面には政治、経済、国際、金融などさまざまな記事が記載されている。たとえ興味がない分野の記事でも、リード文だけには目を通そう。はじめは理解できなくて当たり前。「ふーん、こんな言葉があるのか」くらいの気持ちでOKだ。 興味がない分野の記事にも目を通していれば、世間が何に関心を持っているのかがわかってくる。毎日読んでいるうちに、自分の関心の輪がだんだんと広がっていく。関心のある分野が増えてくれば、多くのものごとが見えるようになってくる。
さいごにリード文のない小さな記事を読む。はじめの2、3段落だけで構わない。新聞記事は、前半部分にもっとも伝えたいことを書いてある。基本的な情報を得るには、前半部分を読むだけで十分だ。すぐに読み終わるだろう。
すべての記事を理解しようとしなくていい。はじめはわからなくて当たり前。とりあえず目を通すのが重要だ。新聞を読む習慣を2ヶ月ほど続ければ、基本となる情報やキーワードは、自分の中に蓄積されているはずだ。
理解できる記事が増えると同時に、自信がつき、新聞を読むのがおもしろくなってくるはず。知識が増えるのは、本来は楽しいことなのだ。
新聞の切り抜きはしないほうがいい。切り抜いたことで満足してしまって、情報が頭の中に入ってこない。情報はいつでも提供できるように頭の中にしまっておこう。切り抜きをする時間があるなら、その分多くの記事に目を通そう。
テレビのニュースや雑誌で情報を追加
 情報収集には、テレビや雑誌など、新聞以外のメディアも利用する。
情報収集には、テレビや雑誌など、新聞以外のメディアも利用する。
ニュースは、コメンテーターの評論があまり入っていない番組がいい。欲しいのはだれかの意見ではなく、情報だ。評論家の意見を聞くのではなく、自分で考える習慣をつけよう。
自分で考える前に他者の発言を耳にしてしまうと、その意見に流されてしまうかもしれない。とくに情報が自分の中に十分に溜まっていない時期には注意したい。その発言が正しいのか、正しくないのかが判断できない。
おすすめはNHKのニュース。なにかと世間を騒がせているNHKだけど、他の放送局に比べれてバラエティー感は少ない。情報だけを効率よく収集できる。
また副音声では英語で聞くことも可能だ。日本語のテロップもついているので、情報収集のついでに英語の勉強もできる。まさに一石二鳥だ。
雑誌でグローバルな視点を身に付ける
電車などの雑誌の中吊り広告は、世間の関心や流行りを手っとり早く知ることができる。通勤のときは、目の届く範囲の中吊り広告にざっと目を通そう。
 雑誌には多くのジャンルがある。忙しいビジネスパーソンは、そう何冊も読めないだろう。せっかくだから、海外の雑誌を読むのはどうだろうか。
雑誌には多くのジャンルがある。忙しいビジネスパーソンは、そう何冊も読めないだろう。せっかくだから、海外の雑誌を読むのはどうだろうか。
たとえば、グローバルな視点を身に付けたい場合には、「ニューズウィーク日本版」がおすすめ。ニューズウィークは、メディアとしての信頼度も高い。
記載されている記事は日本の雑誌とは、かなり違う。日本で生活している限りは考えることないような内容(たとえば飢饉の問題、独裁政治の問題など)の記事が掲載されている。ほかにも、外国人記者の目から見た日本の記事なんかが読める。
海外の雑誌は、自分の関心の幅を広げられるし、日本人とは違った角度でものごとを見る目が育つ。興味がある人はぜひ一度、目を通してみてほしい。
インターネットの情報には注意
 情報を入手するときは、その情報が信頼できるのかを常に疑うようにしたい。
情報を入手するときは、その情報が信頼できるのかを常に疑うようにしたい。
情報は、まずは確実性の高いメディアから順番に集めるように心がけよう。日常的に信頼できる情報に触れていれば、ある程度は入手した情報が事実か嘘かを判断できる。フェイクニュースやガゼネタをつかまされる可能性は低くなる。
偏向報道などと言われることもあるが、新聞やテレビといったメディアは、きちんと取材を行い、しっかりしたソースをもとに情報を発信している。100%ではないけれど、信頼性の高いメディアだといえる。
信頼度に問題あるのは、インターネット上に流れている情報。ネットは、気軽に企業サイトなどの一次情報にアクセスできるメリットがある。その半面、嘘か本当かを判断できないような情報が多く溢れている。
Yahoo!ニュースなどの大手ニュースサイトはソースが記載されている。だけど、その他多くのサイトではソースが不明だ。ネットの情報はうのみにせず、ソースを確認するようにしたい。
ハマりすぎ注意のSNS
![]() いまやスマートフォンは僕らの生活には欠かせない。スマホは、どこにいてもインターネットにアクセスでき、情報を手に入れることができる優れたアイテムだ。
いまやスマートフォンは僕らの生活には欠かせない。スマホは、どこにいてもインターネットにアクセスでき、情報を手に入れることができる優れたアイテムだ。
しかし、便利すぎることは危険でもある。とくにSNS。いつでもどこでもアクセスできるものだから、時間があればのぞいてしまう。他のことが後回しになってしまうがちだ。
SNSはほどほどに。スマホに人生を操られないように注意しよう。
読書は情報を理解する力を育てる


本を読む人は年々少なくなってきている。2014年に文化庁が実施した『国語に関する世論調査』では、47.5%の人が「1ヶ月に1冊も本を読まない」と回答した。2003年の調査では37.6%だった数字が、約10年間で10%も増えた。
「若者の読書離れ」とよく言われているが、年齢別のグラフからもわかるとおり、オヤジ世代のほうが本を読んでいない。スマホばかりいじっている親からでは、本好きの子どもは生まれないだろう。
たしかに読書は効率が悪いし、時代遅れ感が大きい。最新の情報をすばやく入手するという点では、他のメディアには到底かないっこない。だけど書籍には、他のメディアにはない価値がある。情報の深さだ。
忙しい現代人にとっては、情報を効率的に集める能力は必須だ。しかし情報を持っているだけでは、それほど意味はない。情報を理解し、分析し、ビジネスなどに利用してこそ価値があるのだ。
情報をかしこく利用するには、考える力が必要になる。考える力を鍛えるには、本を読むのが1番だ。とくに「自分にはちょっぴりむずかしい」と思うくらいの本をじっくりと読み解くのがいい。
読書は、著者の思考プロセスの追体験だ。筆者の考えを追いながら、理解できるまでじっくりと読み込むことで、思考力は育っていく。思考力が高まってくると、情報を深く解釈できるようになる。他の分野と関連させるなど、応用がきくようになってくる。
読書のあとには、まとめる習慣をつける
本を読み終わったあとには、自分の言葉で内容をまとめてみよう。自分では理解しているつもりでも、実際には理解できていないことが多い。
理解しているかどうかを確かめる方法は、本の内容をだれかに説明してみることだ。わかりやすく伝えられたらわかっているということだし、頭の中がモヤモヤしてうまく言葉にできなければ、わかっていないということだ。
まとめを作ることで、要点を見抜く力が鍛えられる。せっかく時間をかけて読むのだから、知識はしっかりと身に付けるようにしたい。
情報力を高める方法 まとめ