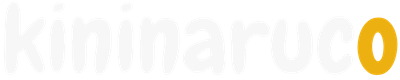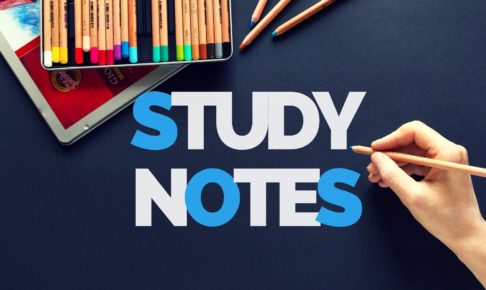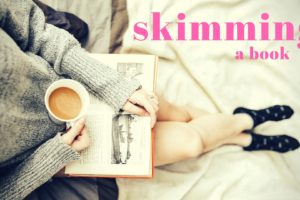学校ではノートのまとめ方は教えてくれない。小学生のとき、先生に教わったのは、ただ板書を丸写しするということだけ。
僕らは先生がまとめてくれたことを、せっせとノートに書き写しているけれど、それで勉強ができるようになるとは思えない。自分ではなにも考えていないもの。
時間の無駄遣いはしないで。いますぐ実践できる勉強ノートのまとめ方を説明します。
mokuji
勉強ノートのまとめ方1;いますぐ板書の丸写しはやめる
 小学生のとき、担任の先生は僕に言った。「ノートは先生の似顔絵を描くところではありません。ノートには先生が黒板に書いたことをそのまま写すのです」と。
小学生のとき、担任の先生は僕に言った。「ノートは先生の似顔絵を描くところではありません。ノートには先生が黒板に書いたことをそのまま写すのです」と。
先生の似顔絵をノートに描くのは、下校途中にピンポンダッシュをするのと同じくらい、小学生にとっては一般的な行動だ。現にクラスの他のみんなも描いていた。だけどそのとき怒られたのは僕だけだった。友人たちの、あいつ怒られてやんの的視線を感じながら僕は先生に謝った。ごめんなさい。もう描きません。許してください。給食は残さず食べます。トイレのあとは手を洗います。
先生に怒られたのは似顔絵スキルが低かったせいだ、もう少し美人に描いてあげればよかったと深く反省した。そして先生の似顔絵をノートに描くのはやめた。でもそれは間違いだった。その決断をしたとき、僕のノートはイマジネーションの場所ではなくなった。板書を写すだけの、ただの紙切れに変わった。この瞬間、ノートは先生に支配されたのだ。
やがて小学校を卒業し、中学、高校、大学へと進んだが、ノートは先生に支配されたままだった。来る日も来る日も、遠足の日と彼女に振られた日の翌日以外は板書を写し続けた。
その姿は、まるで精巧に作られたロボットだった。黒板を見る、ノートに写す、黒板を見る、ノートに写す、首のこりをほぐす、黒板を見る、……この動作を飽きもせず、延々と繰り返していたのだから。高校生のときには50分を6セット、大学生のときには90分を4セット。10年以上も、だ。
もし筋トレのロボットだったら、いまごろは日本のアーノルド・シュワルツェネッガーとして大阪の府知事になっていたはずだ。もしドラえもんだったら、ひみつ道具を使って、あんなことやこんなことができたらいいなだったはずだ。だけどじっさいの僕は何者にもなり得ていない。
社会人になったとき、僕のノートスキルは小学校低学年の男子に少し毛が生えたレベルだった。毛が生えているなら中学生レベルではないのかとか、おれは小学5年生のときにはすでにジャングル大帝レオだったとか、そういう下品なことを考えてしまった人はそっと胸のなかにしまっておいてほしい。僕はきみを評価する。
これ以上無駄話を続けると、続きを読んでもらえなくなりそうなので本題に入る。僕が言いたいのは次の3つだ。
 板書の丸写しを続けているかぎりは、本当の意味で勉強ができるようにはならない。勉強ができるようになるには、小学生のときに先生に教わった「ノートには板書を写す」という言葉を捨て、その習慣をやめること。そして新しいノートのまとめ方を学ぶことだ。
板書の丸写しを続けているかぎりは、本当の意味で勉強ができるようにはならない。勉強ができるようになるには、小学生のときに先生に教わった「ノートには板書を写す」という言葉を捨て、その習慣をやめること。そして新しいノートのまとめ方を学ぶことだ。
それができれば、シュワルツェネッガーにだってなれるし、ドラえもんにだってなれる。僕はほんとうにそう思っている。その方法を伝えたい。
頭のなかに板書をコピーアンドペースト
さっきも言ったとおり、板書の丸写しとは「黒板を見る」→「ノートに写す」を繰り返すことだ。これがどれほどつまらないことかを説明するために、板書の丸写しを焼肉に例えてみよう。
板書の丸写しは、焼肉では「お肉を口に運ぶ」→「お肉をそのまま飲み込む」ということだ。おそろしくつまらない。天国の牛さんや豚さん、鳥さんに失礼すぎる。だれもこんな食べ方はしないはずだ。普通の人は飲み込む前に「10〜30回ほど、牛さんをもぐもぐ味わう」だろう。そして牛さんを味わうからこそ、その味を覚えることができる。ただ飲み込むだけでは、牛さんの味を覚えることはできないし、思い出すこともできない。
この牛さんの例からわかるように、知識を覚えるには板書を味わう必要がある。そうか、黒板を食べればいいんだなと思った人。それは違う。
その方法とは「黒板を見る」と「ノートに写す」のあいだに「ある行為」をはさみ込んであげることだ。

ある行為とは、パソコンでコピーアンドペーストをするように、板書をコピー(マウスで範囲を指定するイメージ)して、コピーした文字を頭のなかに貼り付けるという方法だ。このとき、頭のなかには黒板をイメージしておく。
ノートに写すときには教室の黒板は見ない。頭のなかの黒板を見て、それをノートに写す。この作業をはさみ込むことで、知識は頭のなかに取り込まれる。これが正しい板書の味わい方だ。
わかりやすいようにコピペという言葉を使ったけど「カット(切りとる)」するイメージのほうがしっかりと覚えられる。
一連の動作は「黒板を見る」→「頭のなかの黒板に板書をコピーアンドペースト」→「(頭のなかの黒板を見ながら)ノートに写す」となる。
なんだか簡単な気がするけど、これがなかなかむずかしい。頭のなかで文字がぼやけたりする。だけど、なんども挑戦してみてほしい。そのうち、黒板を見るだけで頭のなかに文字が浮かんでくるようになる。そうすればこっちのもの。新しい記憶回路みたいなものが頭のなかに設置されたということだ。
勉強ノートのまとめ方2;見開き2ページを3分割する
 勉強ノートには、B4またはA4のノートを見開き2ページで使う。この大きなスペースにタイトル(見出し)、板書、気づき、要約、ポイント(3つくらい)を書き込む。
勉強ノートには、B4またはA4のノートを見開き2ページで使う。この大きなスペースにタイトル(見出し)、板書、気づき、要約、ポイント(3つくらい)を書き込む。
それぞれの書き方を説明しよう。
1.タイトル
 タイトル(見出し)は左ページの上のスペースに書く。授業では「何についての授業だったのか」を、自習では「何について勉強をしたのか」を書いておく。
タイトル(見出し)は左ページの上のスペースに書く。授業では「何についての授業だったのか」を、自習では「何について勉強をしたのか」を書いておく。
このとき「日本史の授業3回目」みたいに、授業の内容をすぐには思い出せないタイトルはつけないこと。頭のなかの、どの場所に授業の知識が保存されているのかが、わからなくなってしまう。適当な題名をつけたエクセルやワードのファイルがパソコンの中で行方不明になるのとおなじだ。ノートを見返しても授業の記憶がよみがえってこない。
また「ペリーはどうして日本にきたのかな?」のような疑問系の見出しもおすすめしない。この見出しでは授業の内容を思い出すきっかけが少なすぎる。それにテストの前にノートを見返しているとき、見出しが疑問系になっているとかなりイラっとする。
想像してみてほしい。少しでも知識を増やしたいと思っているときに「どうしてだろう?」と聞かれるわけだ。おしっこを漏らしそうなのに、トイレに入るには、なぞなぞに答えないといけない。そんな理不尽な状況だ。「その答えを知りたいのはこっちだ!」と思わずツッコんでしまうだろう。血圧は上がり精神は乱れる。テストの前には危険すぎる。
タイトルには「ペリーが黒船で日本にきた真相は、日本近海のクジラの油が目的だった」のように、授業の内容をまとめたもの(授業の結論)を書く。ひとめ見るだけで授業の記憶がよみがえってくる。このとき、授業のキーワードをたっぷり含めるのがポイントだ。タイトルに入っている各キーワードが、頭のなかで眠っている授業の記憶を呼び覚ますきっかけを与えてくれる。
2.板書
 板書はノートの左ページに書く。さきほど説明したとおり、コピーアンドペーストを意識して、板書の丸写しにならないように気をつけてほしい。
板書はノートの左ページに書く。さきほど説明したとおり、コピーアンドペーストを意識して、板書の丸写しにならないように気をつけてほしい。
3.気づき 4.要約
 右のページは縦線を引いて左右に分ける。左側は気づきスペース、右側は要約スペースにする。気づきスペースには、板書以外の先生のコメントや自分が授業中に気づいたこと、疑問に思ったことを書き込んでおく。要約スペースには、気づきスペースでの疑問の解消や授業の要約をまとめる。
右のページは縦線を引いて左右に分ける。左側は気づきスペース、右側は要約スペースにする。気づきスペースには、板書以外の先生のコメントや自分が授業中に気づいたこと、疑問に思ったことを書き込んでおく。要約スペースには、気づきスペースでの疑問の解消や授業の要約をまとめる。
この右ページをうまく使えるようになれば、勉強の成果はあがり、学校の成績は伸びていく。それぞれの具体的な使い方はのちほど説明する。
5.ポイント
 さいごに、その授業のポイントを3つばかり選んで、右ページの上の部分に書いておく。ポイントが2つのときは2つでいいし、4つのときは4つ書けばいい。だけど5つ以上はダメ。
さいごに、その授業のポイントを3つばかり選んで、右ページの上の部分に書いておく。ポイントが2つのときは2つでいいし、4つのときは4つ書けばいい。だけど5つ以上はダメ。
ケーキ屋でショートケーキもモンブランもチーズケーキもいちごタルトもシュークリームもお姉さんも食べたいと駄駄をこねるとお母さんに怒られるだろう。そういうことだ。
ポイントをまとめる理由は3つ。
知識に優先順位をつけられるようになれば、授業で指名されたり、だれかに説明したりするとき、ポイントをわかりやすく伝えられるようになる。授業のキーワードを見つける訓練をしておけば、本質を見抜く力が鍛えられる。本質を見抜けるということは、応用力がつくということだ。超かっこいいだろう? ぜひチャレンジしてみてほしい。
勉強ノートのまとめ方3;気づきスペースでストーリーを展開する
 授業中の気づきや疑問を放っておくのは、勉強ができない人の悪いクセだ。彼らは「なぜ?」を放置したまま、教科書やノートのキーワードだけを覚えようとする。そして「どうしてすぐに忘れてしまうんだろう?」と不思議に思う。
授業中の気づきや疑問を放っておくのは、勉強ができない人の悪いクセだ。彼らは「なぜ?」を放置したまま、教科書やノートのキーワードだけを覚えようとする。そして「どうしてすぐに忘れてしまうんだろう?」と不思議に思う。
これは机の上に本を並べて「どうして本は倒れてしまうんだろう?」と悩んでいるようなものだ。答えは簡単。ブックエンドで本を支えていないからだ。
教科書やノートのキーワードだけを覚えようとしても、すぐに忘れてしまう。頭のなかで知識が定着するように、しっかりと支えてあげないといけない。そしてその支えになるのは、授業中の疑問や気づきからはじまる、ひとつなぎのストーリーだ。
だれかの主張に対しては「僕だったらどうするだろう?」、歴史の授業では「今の日本だったらどうだろう?」などと視点を変えてみる。 こうやってキーワードをストーリー化していく。ストーリーとは自分の思考の流れのこと。考えを整理するためのプロセスのことだ。接続詞を使えばストーリーは論理的になり、論理的なストーリーは知識が記憶にしっかりと根をはるための支えになる。そしてキーワードを思い出す手がかりにもなる。だれかに説明するときには、わかりやすく伝えることができる。
こうやってキーワードをストーリー化していく。ストーリーとは自分の思考の流れのこと。考えを整理するためのプロセスのことだ。接続詞を使えばストーリーは論理的になり、論理的なストーリーは知識が記憶にしっかりと根をはるための支えになる。そしてキーワードを思い出す手がかりにもなる。だれかに説明するときには、わかりやすく伝えることができる。
ノートの上でストーリーを展開するときには、矢印(→)を使えばいい。接続詞と矢印を使ってストーリーを見える化しておけば、ノートを見返したとき、自分がなにを感じたのか、なにを考えたのか、そしてその考えをどのように展開させていったのかが手に取るようにわかる。板書の丸写しノートをぼんやりと眺めているよりは、よっぽど効果的な復習ができるはずだ。
矢印以外にも、強調するところは◯や□で囲む、視点を変えるところにはキャラクターを描いて吹き出しにするなど、わかりやすいように工夫をしていけば、オリジナルの見やすいノートができあがる。先生の似顔絵を描くときの公式は、「先生の顔X1.3」が正解だ。
勉強ノートのまとめ方4;要約スペースで授業の本質を見抜く
 勉強が苦手な人は、教科書に書いてあることや先生が言ったこと、黒板に書いてあることをそのまま受け入れる。そして教科書や授業の内容を理解したつもりになってしまう。
勉強が苦手な人は、教科書に書いてあることや先生が言ったこと、黒板に書いてあることをそのまま受け入れる。そして教科書や授業の内容を理解したつもりになってしまう。
理解しているか、理解していないかは、ノートからひとつのキーワードを抜き出して「それはどういうこと?」と自分に聞いてみればわかる。教科書に載っていたからとか、先生が言っていたからとかしか答えられなかったら、本当に理解しているとは言えない。
テストでいい点数をとるだけならそれでもいいかもしれないけど、本当の意味で勉強ができるようになりたかったら、自分の言葉で授業の内容を説明できるようにならなくちゃいけない。それには考える力を鍛えていくしかない。
考える力を鍛えるには、教科書や板書の内容に対して「それってどういうこと?」「なんでそうなるの?」「つまりなにが言いたいの?」と疑問を持つこと。そしてその疑問に対して「こういうことだ!」「理由は〇〇だ!」と自分の言葉でまとめること。これらを書き込むのが要約スペースだ。
要約スペースに授業の内容をまとめておくと、頭のなかに知識が定着しやすくなるし、だれかにわかりやすく説明できるようになる。要約(つまり)は、ものごとの本質を見抜く訓練にもなる。その結果、応用がきく。まわりからは勉強ができる人、頭がいい人と言われ、学校を卒業したあとは仕事ができる人になっていくはずだ。
勉強ノートのまとめ方;まとめ