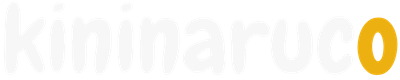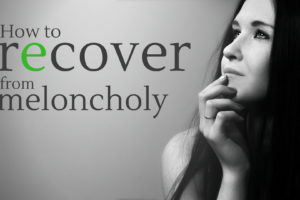タスク管理に悩むビジネスパーソンが多い。タスクリストを作っているのに、予定通りに仕事が終わらないのだ。
原因はタスク管理の方法にある。その日にやりたい仕事をただ並べるだけのタスクリストを作っているなら、いますぐ見直そう。
予定通りに仕事が終わるタスクリストの作り方を紹介する。
mokuji
予定通りに仕事を終わらせたいなら、タスク管理の方法を見直そう!
タスク管理はむずかしい。夕方になると、頭をかきむしるビジネスパーソンがオフィスのいたるところに現れる。朝に作ったTODOリストがまだ半数近く残っているのだろう。見慣れた光景だ。
「今日も予定通りに仕事が終わらなかった」。彼らの心の声が聞こえる。残業が始まる。
タスクリストを作っても、仕事が終わらない理由
なぜ、予定通りに仕事が終わらないのか? ありがちなのが、次の4つの理由だ。
- 1日のタスクリストに仕事を詰め込みすぎている
- 同僚や上司からの頼まれごと、割り込み仕事が多い
- やりたくない仕事になかなか手をつけられず、つい先延ばしをしてしまう
- 仕事を完璧にこなそうとしすぎている
これらの問題は、精神論では解決できない。過去の歴史を振り返っても、明らかだ。
毎日多くのビジネスパーソンが「今日こそは!」と戦いを挑み、返り討ちにされてきた。エナジードリンクでドーピングしても、結果は変わらない。
残念ながら、「がんばる」「ダラダラしない」といった気持ちだけでは、予定通りに仕事は終わらないのだ。
仕事が終わらないのは、タスク管理の方法が原因
予定通りに仕事を終わらせたいなら、タスク管理の方法を見直すのが先だ。精神論を語るのは、そのあとでいい。
まずは作業時間を記録するところから始めたい。どれだけ丁寧にタスクリストを作っても、それぞれのタスクにかかる時間が不確かなら予定通りに仕事が終わるはずがない。
「1時間で終わると思っていた仕事が、実際には2時間かかった」。こういった経験は誰もがあるはず。仕事が終わらないのは、自分の仕事のスピードを正しく把握していないのが原因なのだ。
タスク管理の方法は「タスクシュート式」がおすすめ
では、タスク管理の方法を見ていこう。紹介するのはタスクシュート式と呼ばれる時間管理術だ。
タスクシュート式とは
タスクシュート式は「TODOリスト+α」のタスク管理の方法だ。
1日にやらなければならない仕事(タスク)をリストアップするところまでは、一般的なTODOリストと同じ。違いは、それぞれの仕事にかかる時間の予測(見積時間)と、実際にかかった時間(実績)を記録するところ。
見積時間と実績の差が「見える化」できる。なにが原因で仕事が終わらなかったのかが、数字で表れるのだ。
タスクリストの作り方
タスクリストは下の表のように作る。

書き出すのは「進捗状況」「時間」「タスク」「見積時間」「開始時間」「実績」の6項目。
タスクリストはエクセルで作ると便利だ。一度作ってしまえば、繰り返し使える。
もちろん手書きでもいい。手書きの場合は、付箋を使うのがおすすめだ。タスクや見積時間を書き込んだ付箋をノートや手帳に貼り付けていくと、並べ替えが自由にできる。
自分で作るのがめんどうな人は、ネットで「タスク管理 エクセル」と検索しよう。タスク管理ツールがいくつか見つかるはずだ。気に入ったものを選ぶといい。
タスクリストの使い方
タスクリストの使い方は、次のとおり。一般的なTODOリストとの違いは、2〜4の項目だ。
- 1日のタスク(仕事)を書き出す
- それぞれの仕事にかかる時間を見積もる
- 仕事を始める時に開始時間を入力する
- 仕事が終わったら終了時間を入力する
- 終わった仕事にチェックをつける
「タスクシュート式」タスク管理のメリット
タスクシュート式を使えば、予定通りに仕事が終わるようになる。それぞれの仕事にかかる時間が正しく予測できるようになるからだ。
タスクシュート式では、1分以上かかるすべての行動をタスクリストに書き出す。トイレに行くときも、コーヒーを入れるときも、机の上を片付けてみようと思い立ったときも、だ(トイレやコーヒーは休憩と書こう)。
それぞれの行動にかかった時間を記録していくと、予測と現実で大きなギャップがある事実に気づく。
「5分休憩のはずが10分も経っていた」「資料作成が予測より15分長引いた」。こうした予測と現実のずれが積み重なり、スケジュールが後ろにずれていく。予定通りに仕事が終わらない原因だ。
作業時間を記録し、予測と現実のずれを埋めていけば、正確なタスクリストが作れるようになる。予定通りに仕事が終わるようになる。
また、仕事に優先順位をつけるようになる。
自分の仕事のスピードがつかめると、タスクリストを作った時点でおおよその退社時間がわかる。「タスクリストの見積時間の合計=1日に働く時間」になるからだ。
見積時間の合計が多ければ帰るのが遅くなる。早く帰りたいなら、タスクリストに入れる仕事を少しでも減らしたいと考えるはずだ。「やらなくてもいい仕事」を省き、「やるべき仕事」だけを残すようになる。
予定通りに仕事が終わるタスクリストの作り方
記事の前半で、予定通りに仕事が終わらない理由を4つあげた。もう一度書いておく。
- 1日のタスクリストに仕事を詰め込みすぎている
- 同僚や上司からの頼まれごと、割り込み仕事が多い
- やりたくない仕事になかなか手をつけられず、つい先延ばしをしてしまう
- 仕事を完璧にこなそうとしすぎている
ここからは、これらの問題を解決するためのタスクリストの作り方を紹介していく。
1日を細かく分けて、仕事の詰め込みすぎをなくす
予定通りに仕事が終わらない人は、タスクリストに仕事を詰め込みすぎだ。多い人は3日分くらいの仕事を1日のタスクリストに入れている。
たとえばこんな感じだ。
「今日はプレゼン資料を作ろうかな。A社に見積書も出さないと。そういえば最近、B社に顔を出してなかったな。C社に行くついでに寄ってみよう。担当のDさんが社内にいるか電話しなきゃ。16時から会議もあるけど、なんとかなるよね。あ、交通費の精算もしなくちゃ」。
ここにメールチェックなどの細かな仕事や昼食などの休憩が入ってくる。自分の身の丈に合わないほどの仕事を詰め込めば、終わらないのは当然だ。
仕事を詰め込みたくなる気持ちはよくわかる。
ホテルの朝食バイキングで料理を取りすぎてしまう感覚と似ている。バイキングでは、あれもこれも「食べたい」気持ちが抑えきれず、自分が「食べられる量」を見誤ってしまう。自分の胃袋を過信しすぎるのだ。
仕事でも同じだ。
あれもこれも「終わらせたい」気持ちが強すぎて、自分が「こなせる量」まで頭が回らない。スーパーマンにでもなったつもりでタスクリストを作ってしまう。
どちらにしても、あとで苦しい思いをするのは自分だ。冷静になろう。僕らは普通のサラリーマンだ。
仕事の詰め込みすぎを見つける方法がある。手順を説明しよう。
- 1日を1~3時間ごとのブロックに分ける
- 各ブロックに名前をつける
- ブロックごとにタスクリストを作る
- 見積時間と実績(実際にかかった時間)を比べる
具体例をあげる。
勤務時間が9時から18時の会社だったら、9~12時を「午前ブロック」、13~15時を「午後1ブロック」、15~18時を「午後2ブロック」に分ける。「午前」「午後1」「午後2」のブロックごとに、3つのタスクリストを作る。
1日を細かく分けると、仕事の詰め込みすぎが防げる。
2、3時間という小さな単位でタスクリストを作るほうが、無理な計画になっているときに気づきやすいからだ。8時間という大きな単位では「これくらいできるはず」と気持ちが大きくなりがち。仕事が詰まったタスクリストを作ってしまう。
タスクリストには、割り込み仕事に対応する時間を作る
割り込み仕事はやっかいだ。
割り込み仕事が入ると、それに対応する時間が取られる。さらに、中断した仕事を再び始めるとき、その作業に集中できるまで時間がかかる。思った以上に時間をロスするのだ。
割り込み仕事の対策を考えてみよう。
まず、割り込み仕事が入ったら、すぐにタスクリストに加える。
たとえば、会議の資料を作っているときに、上司に「A社にFAXを送ってほしい。急ぎで」と頼まれたら、タスクリストの「会議資料作成」のあとに「A社にFAX送信」と「会議資料作成(再開)」の2つのタスクを加える。作業時間も忘れずに記録する。
次は、この時にかかった時間を参考にして、翌日のタスクリストに「割り込み対応」の時間を作る。
こうしておけば、仕事を頼まれても、あらかじめ計画しておいた割り込み対応の時間に片付ければいい。急な仕事を頼まれてタスクリストの順番が前後しても、予定がうしろにずれ込むのが防げる。
「順番の見直し」と「レシピ化」で仕事の先延ばしを防ぐ
先延ばし癖のある人は、仕事をする順番がよくないのかも。難しい仕事や時間のかかる仕事は午前中にやってしまおう。
仕事のやる気は1日のうちでもっとも朝が強く、夕方につれて弱くなっていく。睡眠をたっぷり取ったあとの、エネルギーがみなぎった状態のときに、やりたくない仕事を済ますべきだ。
貴重な朝の時間帯にいつでもできる仕事をするのはもったいない。
始業のチャイムと同時にメールやSNSをチェックする人は要注意。それほど頭を使わない作業は疲れていてもできる。午前中にやるのは時間とエネルギーの無駄遣いだ。手のかかる仕事を先にやってしまうほうがいい。
仕事をレシピ化する方法もある。
仕事の順番を変えても先延ばししてしまうほど、どうしてもやりたくない仕事があるなら、仕事の手順を細かく分けたレシピを作ろう。「企画書作成」ならこんな感じだ。
- ノートを開く
- 思いつくままアイデアを書き出す
- 企画書に落とし込む内容を箇条書きする
- 箇条書きに補足を付け足す
- 企画書に挿入するデータを集める
- テキストを作る
- グラフを作る
- テキストとグラフを合わせる
- 校正する
- 企画書ができる
まっさらな状態から仕事を始めるのは、よくない。
いきなりパソコンの画面に向かっても、アイデアはなかなか浮かばない。手が止まったまま、フリーズするだけ。時間ばかりが過ぎていく。思ったとおりに進まないから、仕事を投げ出したくなる。先延ばしをしてしまう。
だからレシピ化する。レシピがあれば、その通りに体を動かしていくだけでいい。
料理ができない人でも、初心者向けのレシピがあればビーフシチューが作れる。一流のシェフが作ったものに比べると味も見た目も悪いけれど、それなりのビーフシチューができあがる。
苦手な仕事でもできるようになるのだ。
レシピを作るメリットは他にもある。
途中で「あとは何が必要だっけ」「次は何をしよう」と悩む時間がなくなるため、仕事のスピードが上がる。作業の抜け漏れもなくなるから、うっかりミスも防げる。
レシピ作りのポイントは、「これだったらできる」と感じるところまで仕事を細かく分けること。仕事を細かく分けるのは、苦手意識を減らし、仕事に取り掛かりやすくするためだ。
できあがったレシピを見て、まだむずかしいと感じるようなら、分け方が足りない。レシピを作る前と感情面でなにも変わっていないからだ。苦手意識が残ったままだと、仕事を始める気持ちにならない。
グリンピースが嫌いなら、グリンピースだとわからなくなるまで刻んでやる。そうすれば食べられる。仕事も、苦手意識がなくなるまで細かく分けてあげればいい。
パレートの法則で仕事に優先順位をつける
完璧主義で仕事が終わらない人は、「パレートの法則」を覚えておこう。
パレートの法則とは、組織の20%の人間が利益全体の80%をもたらすというもの。「働きアリの法則」や「80:20の法則」とも呼ばれている。
たとえば、従業員が100人、利益が100万円の会社だったら、ひとりひとりが等しく1万円の利益をあげているわけではない。10万円の利益をひとりであげる人もいれば、1000円しか利益をあげない人もいる。
パレートの法則を仕事に当てはめてみよう。
資料作成なら「ポイントとなる20%を押さえれば80%の完成度になる」といえる。
社外に出す資料だったら、もう少し手を加えてもいいかもしれないが、社内用なら80%で十分。残りの20%は、体裁を整えるなど、内容と関わりない部分だからだ。
仕事の成果は、費やした時間に正比例しない。ある一定のレベルを超えると、成果が上がりにくくなってくる。無駄な時間ばかりが増えていく。
「完成度が80%の資料を2時間かけて作った。さらに2時間かけて90%まで完成度をあげた」。
はたしてこの2時間は必要だったのか。残業してまでする必要はあったのか。
時と場合による、が答えだ。必要なときもあるし、不必要なときもある。
だから、必要なときは「やる」。不必要なときは「やらない」。それでいい。すべてを完璧にする必要なんてないのだ。求められる完成度は仕事によって違う。仕事に応じてメリハリをつけてやればいい。
そう考えさえできれば、完璧主義はやめられる。